
安全のために「同世代の集まり」で作られた高齢者施設は、気づけば社会との接点が失われた場所になっていた。そんな中、オランダでは高齢者と学生が共同生活を送る施設がある。本記事では、オランダの世代を超えた共生の取り組みを通して、高齢者の居場所に本当に必要なものは何かを考えていく。
なぜ高齢者の居場所は「同世代」でつくられてきたのか

高齢者の居場所は、長い間家族が担ってきた。だが、高齢化にともない日常の介護の継続が難しくなったり、「もし夜中に倒れたらどうしよう」という不安が家族につきまとう。そうした背景から、日本政府は高齢者施設を整える方向へ進んでいった。
高齢者施設には専門スタッフがおり、転びにくい設計がされていて、栄養バランスの取れた食事が出る。安全や利便性という面では、たしかに暮らしやすくなる。ただその代わりに、共同生活のルールに従うことが求められ、自分で決められる範囲は小さくなっていく。
そして、施設は自然と「同世代の集まり」になっていった。高齢者向けの設備や食事、運動プログラムなどを効率よく安全に管理するには、同じような状態の人が集まっているほうが、
施設の仕組みとしては、安全面や運営面で調整しやすかった。しかし、守るためにつくられた場所が、いつの間にか地域から切り離された場所になっていた。
福祉施設の多くは地域から孤立していて、関わる人が高齢者本人とその家族、職員やボランティアといった限られた人たちだけになっている。ある世代間交流に関する研究では、シニア世代で若者と話す機会があるのは約3割で、そのうち8割は別居している親族だったという(*1)。つまり、近所に住む若い人などと接する機会は、ほとんどない。
安全や健康を守ること自体は大切だ。だが配慮が行き過ぎると、高齢者は主体的な存在ではなく、「守られる側」として位置づけられてしまう。同世代が集まる高齢者施設への入居という安全を手に入れる代わりに、社会との接点が少なくなり、その人が何かを選んだり、誰かと新しく出会ったりする余地がどんどん狭くなっていく。
世代を混ぜることで起きていること

もし世代を分けずに暮らしたら、そこにはどんな変化が生まれるのだろう。
オランダ東部の街デフェンターには、高齢者と学生が共同生活を送る施設「Woon-Zorgcentrum Humanitas Deventer」がある。施設では学生が月およそ30時間、高齢の入居者と一緒に過ごすことで、家賃が無料になる制度を設けている(*2)。通常なら月に数百ユーロかかる家賃が、ゼロになるのだ。
ただし、これはボランティアや労働という枠組みではない。一緒にスポーツを観る、誕生日の準備を手伝う、スマホの使い方を教える、体調が悪いときにそばにいる。そういった日常的なやりとりが求められるだけだ。施設長のゲア・シプケス氏は、学生は介護や支援を提供する役割ではなく、「良き隣人」だと述べている。
60歳も離れた世代が同じ屋根の下で暮らすと、何が起きるのだろうか。高齢者は世間から切り離されることなく、学生からSNSやトレンドについて学ぶことができる。一方の学生は、人生の教訓や歴史について学び、ふとした会話の瞬間を大切にするようになる。実際、多くの学生が、Humanitasで過ごした時間が自分を形づくったと語っている。
世代が違うからこそ、「高齢者はこうあるべき」「若者はこう振る舞うべき」という期待が固まりにくい。60歳離れた相手に対して、介護する側とされる側、教える側と教わる側といった固定された関係が生まれにくいのだ。会話も交流も義務ではなく、ただ同じ空間にいる中で、自然に関わりが生まれる余白が残されている。
Humanitasの取り組みは、その後別の場所にも広がった。オランダ・ユトレヒトの修道院でも同じような仕組みが始まり、数人の若者たちが修道女と暮らしている。2023年には、オランダ政府が「世代間共生住宅補助制度」を導入した。この制度では、18〜30歳の若者が、主に55歳以上の高齢者が住む集合住宅に入居する場合、1人あたり月最大200ユーロの補助金が支給される(*3)。若者にも高齢者にも役割はなく、単に同じ住宅で暮らす「世代間共生」を促進することを目的としている。
オランダの事例から見えてくるのは、自然と対等な関係が生まれるような場の設計が人と人の関係を変えていくということだ。
老いの時間に必要なのは、ケアより「関係の余白」かもしれない

高齢者にとって他者との交流は、年代に関わらず精神的な健康を支えるという。孤独や孤立が心身の健康を損なうことは広く知られているが、逆に言えば、誰かとつながっている実感が生きる活力になる。ただ、高齢者が幅広い世代と自然に交流できる環境は、今の日本にはほとんどない。日常生活の中で、若い人と継続的につながる機会がないのだ。
オランダの事例を振り返ってみると、そこには、「何をするか」ではなく「何をしないか」を大切にした設計の工夫があった。家でも職場(学校)でもない、いわばサードプレイスとしての居場所をつくるために、決まったプログラムを用意しない。交流を義務にしない。役割を押し付けない。ただ、同じ空間で暮らす中で、自然に関わりが生まれる余地を残しておく。高齢者を「何かをさせる対象」にしないことが、居場所の質を変えていく。
日本にも、似たような試みがある。神奈川県藤沢市の「ノビシロハウス」は、若者がソーシャルワーカーとして高齢者と関わることで家賃が半額になる仕組みを取り入れている。月に一度お茶会を開き、住民同士がゆるくつながる場もある。こうした試みは、日本でも少しずつ広がり始めている。
少子高齢化が進む日本社会において、高齢者を地域から切り離し、同世代だけで暮らす形が当たり前のように続いてきた。たしかに、安心や安全は手に入る。だが、それだけで十分なのだろうか。社会とつながり続けられるか、幸せを感じられるか。そういった視点で、高齢者の住まいや居場所を見直す必要がある。
厚生労働省が掲げる「地域共生社会」という構想も、その一つだ。これは、縦割りの制度や「支え手」「受け手」という枠を超えて、世代や分野を越えた関わりをつくることを目指している。ノビシロハウスのような取り組みは、まさにその実践例といえるだろう。
制度を整えることは、たしかに大切だ。ただ、本当に問われているのは、高齢者も若者も、お互いに「何かをしてあげる相手」ではなく「一緒に暮らす隣人」として関われる場をどう作るかなのかもしれない。
Edited by k.fukuda
注解・参考サイト
注解
(*1)地域住民の社会貢献・世代間交流の実態と 居住地区内にある「空き家」に対する意識|山梨県立大学
(*2)Bruggen bouwen tussen generaties. 12,5 jaar woonstudenten bij|WZC Humanitas
(*3)Staatscourant 2023, 19743 | Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
参考サイト
社会福祉施設における地域交流に関する研究|信州共同リポジトリ
コミュニティにおける高齢者の居場所|大手前大学
Samenleven in vertrouwen: bezoek aan de Zusters Augustinessen|Provincie Utrecht
高齢者と若者が共生。新しい「多世代型コミュニティー住宅」のかたち|日本財団ジャーナル
地域共生社会の推進|厚生労働省









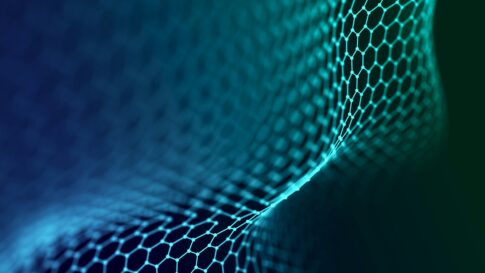













エリ
大学時代は英米学科に在籍し、アメリカに留学後は都市開発と貧困の関連性について研究。現在はフリーライターとして、旅行・留学・英語・SDGsを中心に執筆している。社会の中にある偏見や分断をなくし、誰もが公平に生きられる世界の実現を目指し、文章を通じて変化や行動のきっかけを届けることに取り組んでいる。関心のあるテーマは、多様性・貧困・ジェンダー・メンタルヘルス・心理学など。趣味は旅行、noteを書くこと、映画を観ること。( この人が書いた記事の一覧 )