
ただ訪れるだけの旅から、地域と共生する旅へ。欧州の小都市がマスツーリズムの弊害を乗り越え、観光を「地域再生の手段」として再定義している。環境保全、住民参加、観光資源の再設計という3つの軸から、旅と地域の新しい関係を見ていく。
制度としての「観光の再設計」

欧州では今、観光の意味が書き換えられようとしている。
「European Capital of Smart Tourism」制度の一部門である 「European Green Pioneer of Smart Tourism」は、人口2万5千人から10万人規模の 小都市を対象に、持続可能な観光戦略を評価し表彰する仕組みだ。その背景には消費型観光(マスツーリズム)がもたらした、環境破壊と地域社会の疲弊という痛切な反省がある。
従来の観光モデルは、短期間に多くの観光客を呼び込み、経済効果を最大化することを目指していた。しかし、その代償として、自然環境への負荷、地域住民の生活への影響、地域文化の変容といった課題が指摘されるようになった。観光地が「消費される場所」へと変わってしまう。そうした危機感が、欧州では共有されるようになっている。
この制度が目指すのは、地域・環境・経済の「持続可能な循環」が継続する、新しい観光の形にほかならない。観光が地域を疲弊させるのではなく、むしろ地域を再生させる装置として機能する仕組みである。
対象となる都市は「小規模ながら独自の魅力を持つ」という共通点がある。大都市のような観光資源を持たない代わりに、地域固有の自然や文化、人々のつながりを活用し、環境への配慮だけではなく、観光を通じて地域全体の生態系を再構築しようとする試みである。
持続可能な観光を実現する「3つの軸」

欧州の小都市が実践する観光の再設計は「環境保全」「地域参加」「観光資源の再設計」という3つの軸で支えられている。これら3つの軸は相互に連動しながら機能しており、欧州各地の小都市がそれぞれの状況に合わせて実践を重ねている。
【環境保全】観光と生態系の共存を設計する
自然とは観光資源であると同時に、保全すべき対象である。この認識を制度として徹底している代表例が、イタリア中部に位置するグロッセートだ。
同市は1973年、マレンマ自然公園を設立した。保護区域の約30%は農地として利用され、アグリツーリズム(農業体験型観光)の基盤となっている。この設計は「農業と観光の共存」という理念を具現化したものだ。
公園内には湿地帯が広がり、ガラスワートやシーワームウッドといった塩生植物が自生し、絶滅危惧種であるセイタカシギやケンティッシュチドリが巣を構える。さらにアカウミガメ(カレッタ・カレッタ)の産卵地としても知られ、第二の自然保護区であるディアッチャ・ボトローナ湿地では、200種を超える鳥類と15種のランが確認されている。
グロッセートは観光時間の分散にも注力している。年間を通じた無料ガイドツアー「Raccontare Grosseto」を実施し、繁忙期の集中を避けながら訪問者に環境教育を提供する仕組みだ。観光客の行動を制御し、自然への負荷を軽減しながら地域の価値を伝えている。
ここから見えてくるのは「自然の保護と観光を対立させない」という明確な意思だ。人間活動による影響を把握し、状況に応じて保全策を講じることで、「見せること」と「守ること」を両立させるという基本理念が貫かれている。
【地域参加】住民が観光の主体になる
観光を「地域外から来る人のため」ではなく「地域の人々が主体的に関わるもの」として捉え直す。この発想こそが地域参加の本質と言える。
イタリア北部のマントヴァは、その先進的な実践例の一つである。同市では文化と環境の専門家が連携する、プラットフォーム「ARC3A Mantua」を設立。15の団体が参加し、持続可能なイベント運営を行うための指針を作成している。この取り組みは市内の文化フェスティバルにも適用され、来場者の移動手段から会場で出る廃棄物の量までを徹底的に管理し、観光と文化が両立する新しい持続可能性を示すことに成功した。
さらにマントヴァは「持続可能な目的地宣言」を策定し、地域の観光事業者に署名を呼びかけている。環境保護・社会的責任・経済的価値という3つの原則を掲げ、観光事業者が将来の行動指針として共有すべき価値を明文化したものだ。
マントヴァの事例は、地域参加の新しい形を示している。住民は単に「観光のお手伝い」をするのではなく、観光の設計者であり運営者として、当事者意識を持ちながら豊かさを分かち合う。このような仕組みが、各地で模索され始めている。
【観光資源の再設計】広域連携とインフラで支える基盤
持続可能な観光を実現するには、自治体の境界を越えた連携とインフラの再設計も重要になる。
オーストリアとスロベニアにまたがるカラヴァンケン・ジオパークは、265kmのハイキングトレイルを整備し、国境を越えた広域連携の象徴となっている。ウェブサイトとモバイルアプリ「Geopark Guide」が統合され、訪問者は拡張現実(AR)機能を通じて地域の価値を理解できる。広域連携とデジタル技術の融合が、地域全体を「一つの観光地」として機能させているのだ。
ギリシャ北部のカテリニは、アクセシビリティの再設計に焦点を当てている。海岸に設置された「Seatrac」は、車椅子利用者が自力で海に入ることを可能にする装置であり、障がい者観光の先駆的モデルとして評価されている。
ポルトガルのヴァロンゴでは「クカ・マクカ階段(Cuca Macuca)プロジェクト」が進められ、都市部と山岳部をつなぐ歩行者ルートが整備された。このインフラは観光体験の質を高めるだけでなく、地域住民の日常的な移動手段としても機能しており、観光と生活が同じ空間で交わるように設計されている。
日本の地域観光にとってのヒント

これら欧州の事例は、日本の地域観光にどんなヒントをもたらしてくれるのか。
まず観光の主語を「訪れる人」から「地域」へと転換する発想である。日本の地方都市や離島、中山間地域もまた、観光客数の増加が必ずしも地域の持続可能性にはつながらない現実を経験してきた。
「一体、誰のための観光なのか」を問い直すことが、重要な出発点となる。
この転換が実現すれば、訪問者の役割も変わる。「観光に来る(消費)」から「関わりに行く(参加)」への転換である。欧州の小都市が実践しているのは、訪問者をただの消費者ではなく、地域再生に参加する主体として位置づける仕組みだ。
日本のケースとしては「関係人口」に近いが、その目的意識は根本的に異なる。日本の関係人口は、未来の移住や定住というゴールに向けた「ステップ」と見なされがちだが、欧州モデルでは地域再生への参加自体が旅の目的として完結している。未来への投資か、リアルタイムの価値創造か、目指す方向性に大きな違いがあるのだ。
こうした転換を実現するには、観光を設計する主体が変わらなければならない。欧州の事例では自治体・住民・事業者・環境団体が一体となって観光戦略を描いている点が特徴的である。日本にも地域おこし協力隊やDMO(観光地域づくり法人)といった仕組みは存在するが、それらが「住民自身が観光の設計者になる」ために機能しているかどうかは、検証の余地があるだろう。
欧州の小都市が示したのは、観光を「消費」から「再生」へと転換するプロセスだ。観光の主語が「訪れる人」から「地域」へ変われば、行動が変わる。行動が変われば、関わる人々の意識も変わる。この連鎖が動き出したとき、観光は持続可能な形で循環する力を持つ。まさに日本の地域観光も、同じ問いに向き合う時期に来ているのではないか。
Edited by k.fukuda











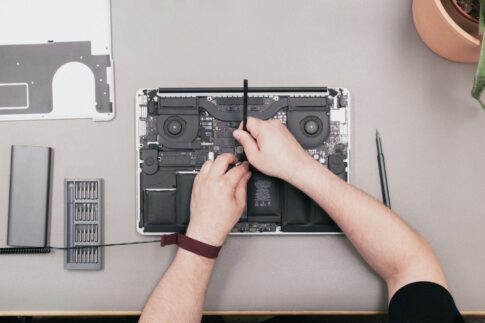

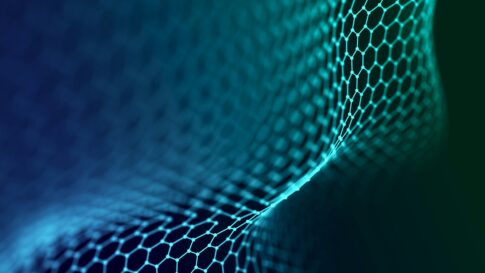










Sea The Stars
大学院で哲学(環境倫理学)を学んだあと、高校の社会科教員に。子どもの誕生をきっかけに、ライターへ転身。哲学や歴史をメインに執筆し、西洋哲学に関する書籍の執筆も担当。厳しい時代だからこそ、寛容さ(多様性)が大事だと考えている。週末は海外サッカー(プレミアリーグ)に夢中。
( この人が書いた記事の一覧 )