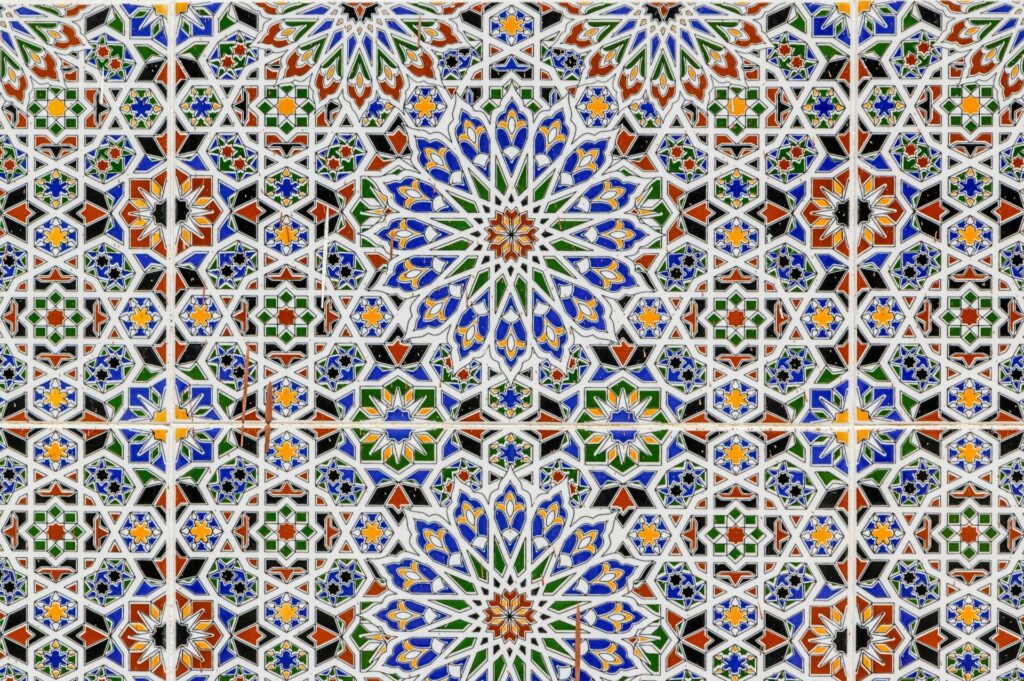
ニューロダイバーシティとは
ニューロダイバーシティとは、「脳や神経に由来する個人レベルでのさまざまな特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていこう」という考え方である。Neuro(ニューロ)は脳、Diversity(ダイバーシティ)は多様性を意味する。
ニューロダイバーシティを推進することで、人材の多様性によるイノベーションの推進や、誰もが活躍できる共生社会の実現が期待される。
これらの目的達成のため、ニューロダイバーシティは、障害の有無にかかわらず「すべての人々」を対象としている。
障害がなくても「チェックが苦手」「コミュニケーションが苦手」な人もいる。そのような得意不得意も含めてあらゆる特性を多様性として包括する。
ニューロダイバーシティの国際的な取り組みのきっかけを作ったのは「スペシャリステルネ」というデンマークの企業だ。同社は、自閉症のある方にソフトウェアテスターの適性があることに着目し、ソフトウェアテストコンサルティング業を開業。自閉症をもつ人材を、競争力として採用した。この取り組みの成功と意義に注目した多くの企業が、ニューロダイバーシティに取り組んでいる。
ニューロダイバーシティに取り組むべき理由

ここでは、企業などにおいてニューロダイバーシティに取り組むべき理由を3つ解説する。
1.多様性はイノベーションを生み出す源泉
多様な価値観や発想力は、イノベーションや新しい付加価値を生み出す源泉となる。他人と同じことができる・考えられるのは、裏を返せば差別化が難しいとも言い換えられる。多様な考え方や特性が、既存の枠を超えた発想を生み出すことも多い。
例えば、自閉症(ASD)の方は、傾向としてコミュニケーションが不得意とされている一方で、優れた記憶力や几帳面さを兼ね備えている。また、注意欠如・多動症(ADHD)の方は、注意力や集中力を保つことに難しさを感じやすい傾向にあるが、臨機応変さや創造性に富んでいることが多い。
この他にも、人にはそれぞれ得意不得意が多少なりともある。このような多様性を受け入れることで、異なる視点やアプローチを通じてイノベーションを促進し、組織や社会全体の創造性や生産性を向上させる効果がある。
2.働き方の個別最適化により優秀な人材を獲得・企業の競争力も向上
多様な人材が集う中で、一人ひとりが働きやすい環境を整備することで、優秀な人材の獲得や従業員のモチベーションアップにつながることから、企業の競争力を向上させる。
後天的な大人の発達障害やグレーゾーンも話題になっているように、障害認定をされてなくても、生きづらさや個別支援を必要としている人がたくさんいる。そういった人々への着目は、スムーズに助け合うための業務効率化や、他人への理解を深める人材育成のきっかけとなる。
企業内における多様性の相互理解は、顧客や市場に対する深い理解につながり、マーケティングや商品開発においても競争力を強化する可能性がある。
3.「誰一人取り残さない」共生社会の実現
ニューロダイバーシティへの取り組みは、SDGsの理念の一つである「誰一人取り残さない」共生社会の実現にも不可欠である。
脳の特性による不得意が原因で、一般的な面接や職場で能力を評価してもらえなかった人々は、心身に支障をきたしてしまうこともある。こうしたきっかけで療養生活や引きこもりから抜け出せずにいる人々の社会参加を支援できれば、個人の幸福だけでなく、社会全体にもプラスとなる。
多様な人々が生き生きと暮らし働ける共生社会の実現のためには、型にはまった一律の評価方法を見直し、一人ひとりの能力を最大限に引き出せる環境の構築が必要だ。
雇用に関するニューロダイバーシティの取り組み事例
ここでは、雇用の場面におけるニューロダイバーシティ取り組みを2つ紹介する。
1.採用が進んでいるデジタル分野|経済産業省も推進

IT業界などのデジタル分野では、採用の場面においてニューロダイバーシティの考え方を取り入れる動きが進んでいる。発達障害のある人がもつ特性(発達特性)は、特にデータアナリティクスやITサービス開発といったデジタル分野の業務とうまく適合する可能性が指摘されているからだ。
ソフトバンク、マイクロソフト、ヤフーなどの企業においても成功事例が多くあり、デジタル化などの急速な変化が進む社会において、企業の成⾧戦略として注目を集めている。
一方で、発達特性によりコミュニケーションが苦手であったり、条件が揃わないと集中力が続かない方もいる。そのため、能力を十分に発揮するためには、周囲の支援や配慮も欠かせない。企業が適切な配慮のもと障害をもつ方を積極的に登用し、障害特性に応じて能力を発揮できる環境を整備していく必要がある。
この動きに着目した経済産業省は、少子高齢化による就労人口の減少への対策や企業の競争力の強化を図ることを目的として、ニューロダイバーシティの推進に取り組んでいる。具体的な取り組みとしては、セミナー主催のほか、「デジタル分野における『ニューロダイバーシティ』の取組可能性にかかる調査」(*1)を実施している。
2.日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト
武田薬品工業株式会社(本社:東京日本橋)が企画・運営する「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」は、「ニューロダイバーシティ」の認知を拡大するため、日本橋にゆかりのある企業・団体の賛同を募りながら啓発活動を行っている。
この取り組みは、「商品である医薬品だけでなく、療育環境や生活環境という面からも患者に貢献したい」という思いがきっかけで始まった。具体的には、発達障害のある人に対する、インクルーシブ(包括的)な社会的土壌の創出、発達障害のある人との、相互理解を促進するツールの配付、ワークショップなど啓発活動の企画・主催を行っている。同社を中心として、ニューロダイバーシティを普及させ、誰もが生きやすい社会の実現を目指す。
教育に関するニューロダイバーシティの取り組み事例
ここでは、教育に関するニューロダイバーシティの取り組みについて、以下の2つを紹介する。
1.オーストラリア|多様性を包摂するインクルーシブ教育
オーストラリアの教育現場では、ニューロダイバーシティの考え方のもと、障害などの多様な特性をもつ生徒も含めたインクルーシブ教育が推進されている。個々の学習スタイルやニーズに合わせた教育を提供することで、すべての生徒がそれぞれのペースで成長し、能力を発揮しやすい環境を整える。
2005年に教育のための障害基準が制定されたことをきっかけに、特別支援学校・学級を廃止し、すべての子どもたちを一般学級で教育する方向へシフトした。
2019年からは、オーストラリア・メルボルンのラトローブ大学でニューロダイバーシティプロジェクトが開始。このプロジェクトは、発達障害をもつ学生・スタッフの専門能力開発・学習スキルをサポートするものだ。同大学の教授は「ニューロダイバーシティ促進のためには、障害に対する合理的な調整を提供するだけでなく、個々の強みに基づくアプローチをとるべきだ」という見解を示している。
2.東京大学|ニューロダイバーシティの研究・講演の主催
東京大学は、ニューロダイバーシティを日本でも実現していくため、積極的な研究や講演を行っている。
ソフトバンクと協創して進めるBeyond AI研究推進機構において、自閉症の人々が見ている世界を体験するシステムを用いて、認知個性そしてニューロダイバーシティへの理解を深めようとする研究を実施。
また、筑波大学と共同で講演「ニューロダイバーシティ&インクルージョンシンポジウム」を開催。障害者差別解消法(*2)に基づく権利保障の観点から、多様な発達特性を有する学生の才能を引き出すのに必要な高等教育・就労支援のあり方を議論した。
ニューロダイバーシティ推進における課題
ニューロダイバーシティを推進するためには、まず社会全体での意識改革や教育の改善、法制度の整備などが必要だ。目に見えない違いや特性があるということを理解し、日常のふとした時に意識することが大切だ。
また、ニューロダイバーシティの視点を社会に根付かせるには、多様な特性に合わせた具体的な仕組み・環境づくりも必要となる。以下のような合理的配慮を社会の中で定着させるためには、場面ごとでの個人の判断に依存するのではなく、仕組み化が欠かせない。
- 建物のバリアフリー化
- サイン、音声ガイド、ピクトグラム表示などのユニバーサルデザインの採用
- 照明やデスク配置など執務・学習スペースの工夫
- チームでのコミュニケーション支援
- 聴覚優位の人には音声によるフォローアップ
- 視覚優位の人には文字や図解を活用
企業であれば「どこに何があるのか」「どのように仕事をしたらいいのか」がすべての人にとってわかりやすいと、生産性は大幅に向上するだろう。学校では、教師や支援員の将来的な負担が減り、子どもたちは個々人のニーズに合わせたより良質な教育を受けられる。
このように、個人個人が社会の中に存在する多様性を認識すると同時に、仕組み・環境づくりを通じて、無意識のうちにも多様な違いに配慮できるようにすることが、ニューロダイバーシティを社会で推進していくために重要となる。
まとめ|ニューロダイバーシティは共生社会を実現する鍵
ニューロダイバーシティは、共生社会を実現する鍵となる考え方だ。年齢や性別、国籍など、外見から判断しやすい多様性には徐々に理解が進んでいる。だが、発達特性に対しての理解はまだまだ日本社会に浸透していない。
ニューロダイバーシティについてより多くの人が認識し理解を深めることで、もし誰かが一般的に期待されることを実践できない場合でも、安易に退けられることが減るのではないだろうか。これは単に、当人への配慮というだけでなく、他のメンバーにとっても、違いを受け入れてくれる組織やコミュニティへの信頼感や安心感にもつながるはずだ。
見えない多様性が受け入れられ、いずれ「違いがあって当然」という前提のもと人々のコミュニケーションやコミュニティの形成が進むことを期待したい。
Edited by k.fukuda
注解・参考サイト
注解
*1 『ニューロダイバーシティ』の取組可能性にかかる調査」による
*2 障害者差別解消法による
参考サイト
ニューロダイバーシティ | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI)
Neurodiversity at Work
ニューロダイバーシティの推進について (METI/経済産業省)
日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト
製薬の街を起点に、誰もが生きやすい社会を作りたい。「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」が目指す未来とは? | BRIDGINE ブリジン
オーストラリアで推進されるインクルーシブ教育と ニューロダイバーシティ視点での学習支援の拡大 | 未来コトハジメ
令和5年度 東京大学秋季入学式総長式辞
【PHED×RADD共催】 ニューロダイバーシティ&インクルージョンシンポジウム | PHED – [東京大学]障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事業
ニューロ・ダイバーシティ ~多様性を進化させ、競争力を高めよう





















